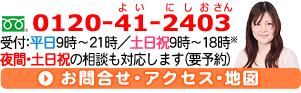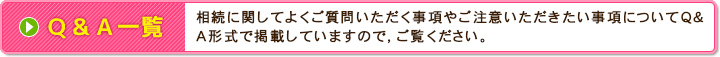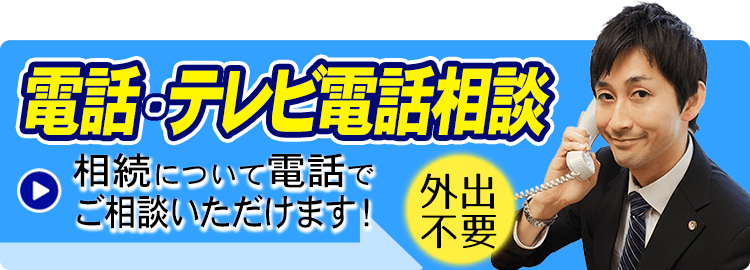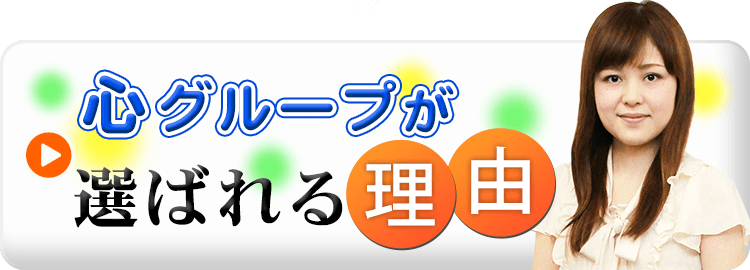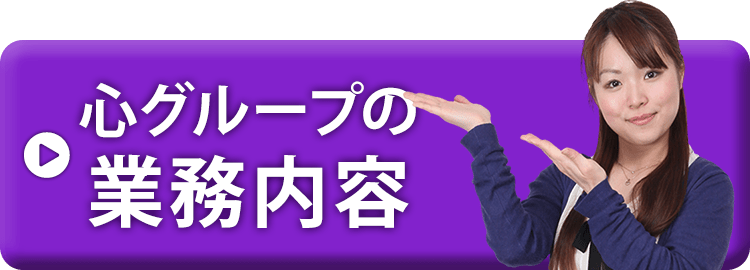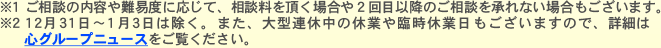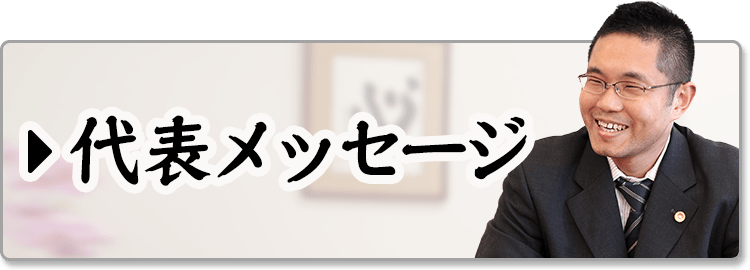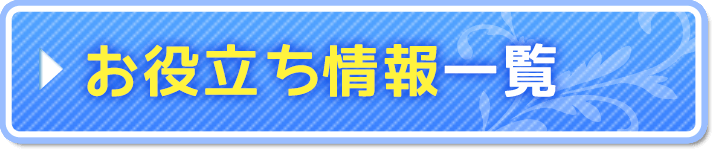法定相続人がいない場合の手続き
1 相続財産清算人について
被相続人に相続人がいない場合、遺言書がある場合には、基本的には、遺言執行者がその遺言書に従って処理を行います。
遺言書もなかった場合や、遺言書の内容によっては、相続財産清算人の選任が必要になります。
また、法定相続人がいたものの、全員が相続放棄をしたことで相続人がいなくなった場合も、相続財産清算人の選任が必要になります。
相続財産清算人は、被相続人の遺産を整理し、特別縁故者がいて分与が相当な場合には遺産の分与などを行い、残余財産を国庫に帰属させます。
以下、相続財産清算人の具体的な業務についてご説明します。
2 相続財産清算人選任申立て
相続財産清算人は、家庭裁判所が利害関係人または検察官の申立てにより選任をします。
利害関係人には、相続放棄をした人、共有持分の取得をしたい人、被相続人に対して債権がある人などが含まれます。
3 選任公告
裁判所が相続財産清算人を選任すると、その旨を官報に掲載します。
4 相続財産清算人の具体的な業務
相続財産清算人は、まず、相続人捜索の公告を行います。
相続人がいるのであれば、その人に相続財産を引き継ぐためです。
また、相続財産にどのようなものがあり、それがいくらになるのかを把握していきます。
官報公告をしても相続人が現れなかった場合、不動産の売却などは、本来、相続財産清算人の権限の範囲外であるため、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てを行い、許可を得て売却をしていきます。
このようにして、相続財産は現金化されていきます。
5 特別縁故者に対する相続財産の分与
内縁の配偶者や療養監護に努めた人、その他の特別の縁故があった人などは、特別縁故者として、家庭裁判所に相続財産の分与の申立てを行うことができます。
家庭裁判所は、このような人の申立てがあった場合、相当と認められるときには、清算後に残存する相続財産の全部または一部を与えることができるとされています。
6 残余財産の処分
現金化されていった相続財産は、国庫に帰属させることになります。
不動産や株式などについては、そのまま国庫に帰属させる手続きもあります。
また、相続財産に共有持分がある場合、その共有持分は、他の共有者に帰属します。
7 報酬付与手続き
国庫帰属させるにあたって、相続財産清算人は、家庭裁判所に対し報酬付与の申立てを行い、報酬を受領します。
8 終了
一通りの手続きが済むと、相続財産清算人が管理終了の報告を家庭裁判所に行い、家庭裁判所が相続財産清算人の選任審判の取消しをして手続きが終了します。
ここまで、法定相続人がいない場合の手続きについてみてきましたが、簡単にいえば、相続財産清算人が選任され、相続財産を現金化して、その中から相続財産清算人の報酬を引き、残ったものが国庫に納められることになり、遺産が整理されていくということです。
認知症の疑いがあると、遺言を作成しても無効となるのか 相続手続きの種類