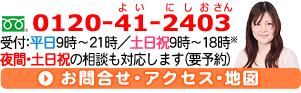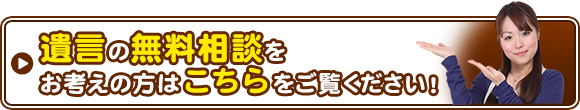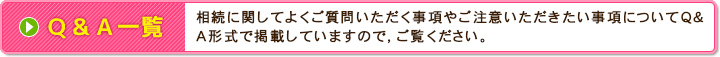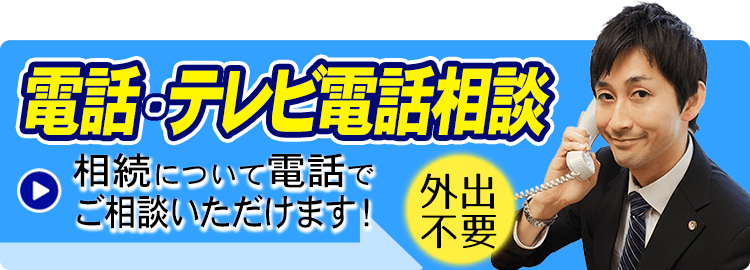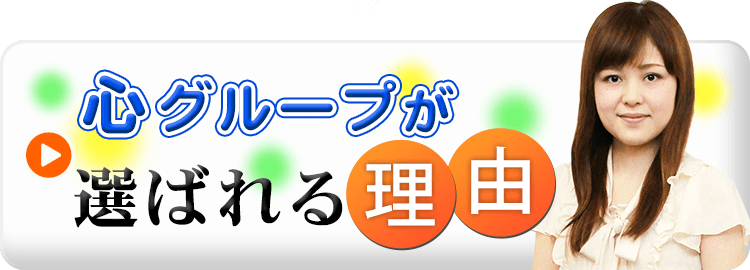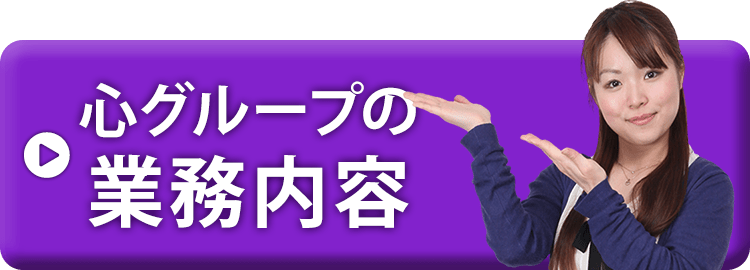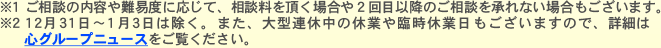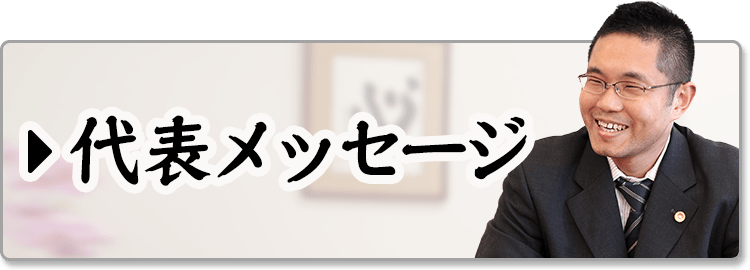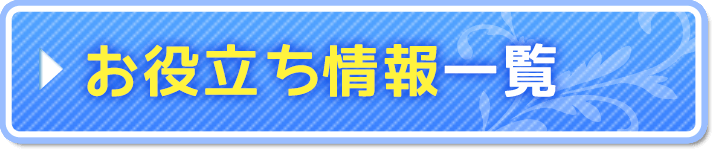認知症の疑いがあると、遺言を作成しても無効となるのか
1 遺言の作成には遺言能力が必要
遺言は、遺言能力がなければ作成できないとされています。
遺言能力があるとされるためには、①15歳以上であることと、②意思能力があることの2つの要件が認められる必要があります。
認知症の疑いがある場合に、上記要件のうち②意思能力があるかが問題となることが多いです。
とはいえ、認知症があるからといって、ただちに意思能力が認められないというわけではありません。
認知症の疑いがあったとしても、遺言の内容が複雑であるかどうか、遺言内容が合理的であるか、遺言の動機、遺言者と相続人および受遺者との関係等を総合的に考慮して、遺言能力の有無が個別具体的に検討されることになります。
2 遺言内容が複雑か
例えば、「遺言者の遺産を全てAさんに相続させる」という遺言と、「遺言者の遺産のうち、X銀行の預貯金はAさんに、Y銀行の預貯金はBさんに、不動産はCさんに、株式はAさんとBさんにそれぞれ相続させる」という遺言がある場合を考えます。
どちらが遺言能力を認められやすいかというと、前者のほうがシンプルですので、そのようなシンプルな遺言のほうが認められやすくなる傾向があります。
3 遺言内容が合理的か
例えば、遺言者には長年連れ添った配偶者がいるにもかかわらず、「相続人ではない人に全ての財産を遺贈する」という遺言があり、特にその理由等も何も示されていないような場合、遺言内容の合理性に疑義が生じます。
遺言者は遺産の分け方を自由に決められるのが原則ですので、上記のような内容の遺言を定めることも可能です。
しかし、客観的にみれば、長年連れ添った配偶者がいるにもかかわらず、なぜその配偶者に遺産を与えないのか疑問が生じます。
そのようなケースで、遺言者に認知症の疑いがあると、「遺言者に遺言能力がないから合理性のない遺言を作成したのではないか」と疑われる可能性があります。
遺言能力を検討する際は、このような遺言の動機、遺言者と相続人および受遺者との関係等も踏まえながら、遺言内容に合理性があるかどうかも考慮されます。
4 長谷川式認知症スケール
長谷川式認知症スケールとは、認知機能のレベルを推定するための簡易的な知能検査のことをいいます。
このテストは30点満点で、20点以下の場合は認知症の疑いがあるとされています。
このテストの点数が悪いからといって直ちに遺言能力が否定されることにはなりませんが、遺言能力を検討する際の参考とはされています。